日本の経済活動を支えているITを担う、責任と矜持
まずは、お二人がそれぞれ率いるシステムコンサルティング事業部と情報システム部がどのような役割を担っているのか、具体的に教えてください。
-
森貞
- プロネクサスは、企業のお客さまのディスクロージャー(経営に関する情報の開示)を支援する事業で実績を重ね、いまではこの分野におけるリーディングカンパニーとして評価されています。その原動力が、独自に開発した開示書類作成支援システムのPRONEXUS WORKSであり、私が統括するシステムコンサルティング事業部がその企画、設計、開発、運用、テクニカルセールスまでを横断的に担当しています。
-
酒井
- 私が率いる情報システム部は、グループ内で使用されるITインフラから業務アプリケーションまで、システム全般の企画設計と構築運用を手がけています。また近年、プロネクサスでは新たなサービスが続々と立ち上がっており、それを実現するシステムの開発も託されています。
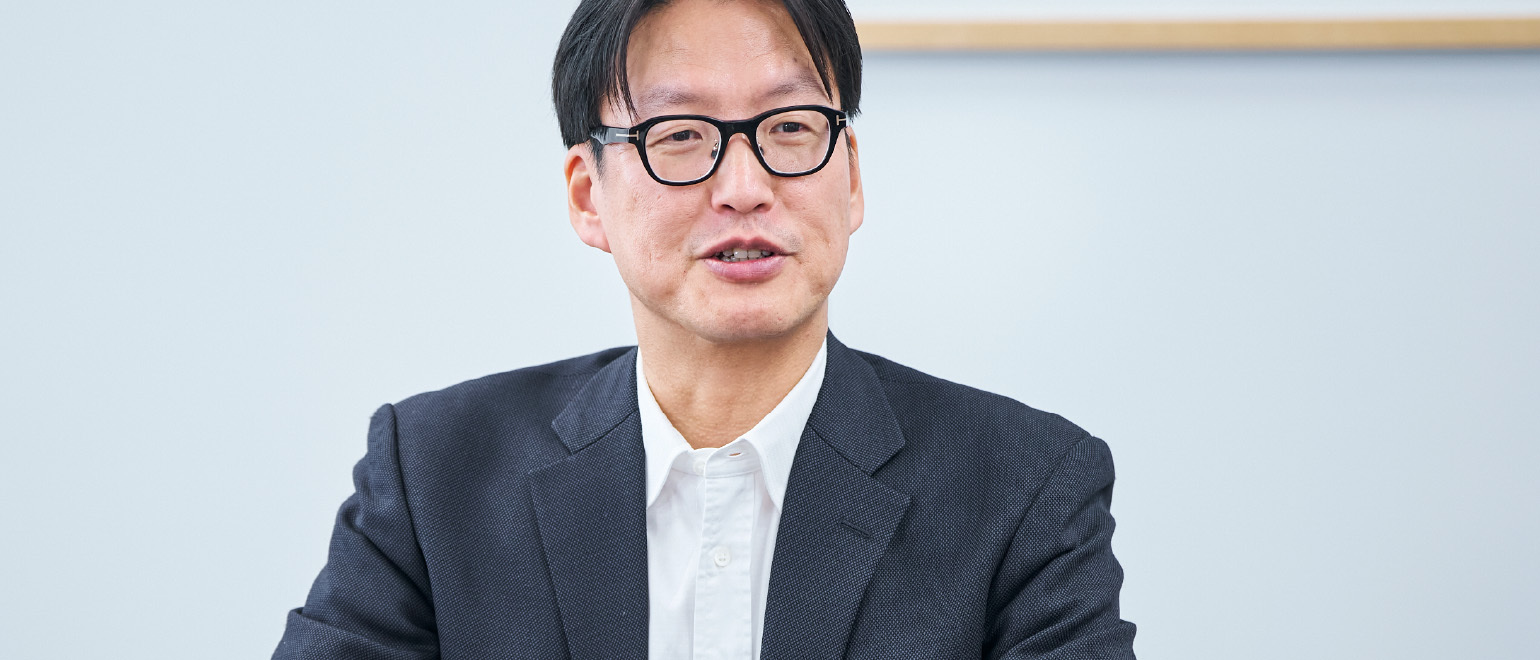
プロネクサスは日本の経済活動に直結するサービスを展開し、お二人の部門はそれをITで支えています。自らの使命や責任をどのように感じていますか。
-
森貞
- 株式会社には、自社が発行する株式を資本市場経由で不特定多数の投資家に購入してもらうことで資金を調達して経営し、利益を得て企業価値を高めるという本質的な特性があります。ここから、「(投資家への)説明責任」が生じており、ディスクロージャー制度はこの説明責任を果たすための重要な社会制度です。さらに最近では、企業の社会的責任、環境・人に優しい持続的成長の観点から、この説明責任の対象が、売上高や利益などの財務情報を中心としたものから、サステナビリティ情報などの非財務情報を多く含む内容へ、より複雑化・高度化しています。また加えて、これらの説明情報を“XBRL”という特殊なデータフォーマットで作成し電子開示することが求められていたり、日本語だけではなく英語でも同時に開示しなければならなくなっています。ディスクロージャーは企業にとって非常に重要な責務ですが、「もし自分が担当したらとても大変! 一筋縄ではいかないな……」と感じるような、きわめて負荷の大きな業務なのが実情です。
この開示内容を作成する業務を、できるだけ簡単・スピーディにチーム共同作業で進行できるITシステム/サービスとして実現したのがPRONEXUS WORKSであり、2,300社超の上場会社のお客さまにご導入いただいています。世界中の数ある仕事のなかで開示業務はほんの小さな一領域にすぎませんが、この一領域を全力で支え、資本市場の健全な運営と発展に専門的に貢献している、そんな仕事を我々は担っています。システムの小さな機能一つをとっても、素晴らしい出来栄えの機能であればお客さまの開示業務の効率性・正確性を格段に向上させ、感謝されることが多々ある。そこに喜びと誇りを覚えながら、私はこの事業に取り組んでいます。
-
酒井
- 私も同じ思いです。いまやプロネクサスの事業にITシステムは不可欠であり、確実に開発運用していくことはもちろん、お客さま向けのシステムも絶対にダウンさせてはいけない。プロネクサスは上場会社の法定開示支援のほかに、投資ファンドが投資家を募集する際の情報開示や、IPO(新規公開株式)を目指す企業のお客さまの支援なども手がけており、サービスの基盤となるシステムは我々情報システム部が構築しています。そこで扱うのは、外部に漏れてはいけないお客さまの機密情報であることが多く、万全のセキュリティ体制を敷かなければなりません。もし、万が一システム事故を起こしてしまったら、お客さまの事業を止めてしまうのはもちろん、日本の経済活動にもインパクトを与える恐れがある。自らが担う責任の重さを絶えず感じていますが、それがやりがいにもつながっています。




